166・タフス祭夫婦善哉珍道中(下)
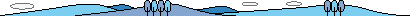
タフス大学学園祭に来て、我が子ポーシャがバンドで演奏をするところをカメラで撮ったし、目にも焼き付けた。世界のグルメもちょっと食べた。あとは展示を回ってみよう。
チアリーディング部。女の子が踊ったり組体操をしたりしている。ぽんぽん飛ぶたびに歓声が沸き上がる。これは見てよかった。投げ飛ばされて竹とんぼのごとく錐揉みをしている学生もいる。たとえが古いな。それを地上で男子がキャッチしている。抱きとめている。そんな青春があるのか。私の青春は寮で「ベストプレープロ野球」や「信長の野望風雲録」ばかりやっていたのに。
チア部のステージは写真撮影禁止である。もちろん写真は撮らない。
「すみません」 実行委員に声をかけられた。一眼レフが目立つのであろう。
「大丈夫です、撮りませんから」
一分後。
「何度もすみません、やっぱり、カメラを鞄にしまってもらっていいですか」
疑惑を持たれている。
ケルト音楽同好会。ゆるい雰囲気。司会も「ここで語勢を強くして拍手をもらおう」なんて思っていない。定番の楽器紹介で、同じ楽器を持っている人が二人いた。司会が楽器名を言ってから、二人が目を合わせて「どうぞどうぞ」なんて譲り合っている。ノンリハーサル。
ここではヴァイオリンをフィドルと呼ぶ。「フィドラー・オン・ザ・ルーフ」のそれだ。フィドラーが五人もいる。育ちがお嬢様お坊ちゃまなのか。
廊下でダンサーがリハーサルをしている。これはアイリッシュダンスが始まるに違いない。
と思っていたが、ただの練習をしているバレエ同好会の人だった。
吹奏楽団。大学生の『宝島』に胸を打たれる。宝島と言えば、学生時代JICC出版の本を読んで大人の世界を知った気分になっていた黒歴史を思い出す。ろくなことを思い出さない。
サンバ同好会。大盛り上がり。若者のパワー。サンバの指揮者はクラシックの指揮者と違い、リズムは取らないが、野球の監督のようにサインを出すということを学んだ。
けん玉同好会。けん玉を横に10個つなげた「10連けん玉」が子供に人気。やってみたかったがおじさんとしてはちょっとね。
場内にはサンドイッチマンや広告ボードを持った学生たちがたくさんいる。なんだろうとボードをじっと見ると学生は立ち止まって見せてくれる。なんて優秀な。
派手なドレスを着た女子学生からフライヤーをもらった。写真を見ればドレスというかほぼ水着である。
「ベリーダンス同好会」
父親としては複雑な気持ちである。難しい勉強をして大学に入ったのに夜は半裸で踊るのか。パパショック。
いやそう思う方が考え過ぎであって、派手なメイクと綺麗な衣装を来て、非日常的な空間で身体表現ができる立派なサークルである。千夜一夜物語の雰囲気が好きな人もいるであろう。
そうだ、ベリーダンスを研究しにいこうよ、スージー。
「駄目」
キーホルダーに名前を書いてくれるサービスがある。なんと100円。もちろん日本語やローマ字ではなく、学生が学んでいる言語で書いてくれるのだ。今いる学生はアムハラ語とハングルともう一つ。ハングルならわかる人もいるかもしれないな。ハングルお願いします。
「今日はどうしてこちらにいらっしゃったのですか」
「娘がバンドに出ているので」
料理の注文と、カメラを注意されるのを除くと、学生さんとお話するのは初めてかもしれない。
「どうしてハングルを選んでくれたんですか」
「学生のころ旅行に行ったことがあります」
「いいですね、私まだ韓国に行ったことがないんですよう。どこがお勧めですか」
もう三十年も前のことなので忘れている。明洞(ミョンドン)や景福宮(キョンボックン)、仏国寺(プルグクサ)なんて学生さんのほうがよくご存知だろう。
「北朝鮮の国境近くで向こうを見ました。また近くの港町のイカの刺身がおいしかった。ソウルで食べた焼き肉が最高でした。サンチュで包んで食べるの」
子供の会話だ。
スージーもポーシャもピアノを弾くので(ポーシャはいないが)ピアノ同好会へ。真面目なサークルのようでトークも一切なしで紹介と演奏が進んでいく。お互いの演奏をデジカメで記録している。デジカメは三脚の上でなく、会場装飾に使われたはずの養生テープの上に乗っけられている。質実剛健。
女性ピアニストが前に立った。ヒジャブのような布を頭に巻いている。名前は日本語。女優さんのような綺麗なお名前である(偶然だがその名前でグーグル検索すると別人の女優が出てくる)。
「曲は、『ああ電子戦隊デンジマン』です」
ヒジャブをまとった学生さんは「でっでごでっでごでっでごててー」とイントロを引き始めた。
「デン、デンジマン、デン、デンジマン、…」
弾き語りではないので歌詞があるわけではないが、昭和生まれには歌が聞こえる。
しかしどうしてですかヒジャブさん。イスラーム世界を学ぶ大学生がどうしてデンジマンに出会ったのですか。急げデンジマン、デンジスパークだ。
ポーシャのバンドの曲はほとんど知らないが、デンジマンは知っている。なんなら歌える。調べるとデンジマンの放映は1980年。バトルフィーバーJと太陽戦隊サンバルカンの間だ。四十年の時を超えて今デンジマン。
/~戦いの海は牙でこげ 悲しみの海は愛でこげ
いい歌だな、デンジマン。
翌日、ヒジャブさんは学内観光ツアーを引率していた。お忙しい。ただしヒジャブにはおびただしい数の缶バッジが装着されていた。ヒジャブに缶バッジをつけてもいいのか。イスラーム世界的に。
ポーシャの二度目の演奏を見たので帰宅する。帰宅とは秋田に帰ることだ。早めの晩ご飯を食べて東京駅の改札をくぐる。くぐれない。ぴぴーぴぴー。自動改札に捕まる。機械、うるさい。秋田に帰れないのか。私だけ。駅員さんが駆けつける。改札一つ通る力がないのか。三回連続改札で引っかかった男である。もう泣きそう。自分の顔だから見えないだけで泣いていたかもしれない。
「最初に乗ったときにうまく記録に残らなかったことが原因のようです」
田舎にスイカは早かった。
秋田に帰る新幹線こまちはすいていて、乗客はみな口を半開きにして魂の抜けた顔で眠りこけていた。このうらぶれ感。
秋田到着。宿敵改札に挑む。四度目。スイカタッチダウン。しゅるっ。きっぷが出てきた。
「やったぜベイビー!」「おめでとう!」「I got it!」
人生で初めて、スイカで改札を通過できました。スージーも私の声に驚く。今回の旅、ハッピーエンド。
――エピローグ――
ローカル線へ。もうこれに乗るだけだ。
「きっぷがない」
スージーが青ざめている。
「さっきの改札で取るのを忘れたかも」と戻る。
スーツケース二つを握って待つ。「なかった」
まだ終わらないのか。そんなドラマはいらない。最悪、秋田から地元までの電車賃を払えばいいだろう。
停車中にワンマン運転手に相談。
「そういうことでしたら、そのまま降りてください」 あっさり解決。ありがとうJR東日本。一人でなくて夫婦というのも信用の材料だったかもしれない。
「パトリックが大喜びしているからそっちに気を取られて」
スージーさん、負け惜しみ。