151・ドラゴンアイ
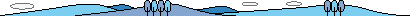
子供が家を出てから、一人旅をするようになった。
子供に家出をされたわけではない。そうだったら雑文など書いている場合ではない。
それでは妻と出かけたいが、妻はクルマに酔いやすい。子供と一緒だったらディズニーランドまで出かけたが、私と一緒だったら隣町に行くのも尻が重い。いや腰が重い。
ガイドブックをめくったりネットを見たりすると、「八幡平ドラゴンアイ」が気になった。
「八幡」とはどう読むのか。
鉄工所の「やはた」か。京都の岩清水の「やわた」か。全国的に数が多い「はちまん」か。
いやそこではない。
ドラゴンアイとは円い池の雪が解けるとき、水がリング状に見え、青い瞳のように見える状態のようだ。五月ころの限られた時期にだけ見える自然現象である。いいな。
ドラゴンアイができているかは現地に行ってみないとわからない。それもドラマティック。
妻を誘うがいつものように返事をしない。義母を誘っている。義母はふだん出かけることがないのでどこにでも行きたい。「○時になったら出発するよ」と告げる。
当日。やはり一人で家を出る。観光地には駐車場があるだろうから、クルマをちょっと停めて、一眼レフで写真を撮って、ラーメンでも食べて帰ろう。
道中、特筆すべきことなし。ただトイレのタイミングだけを考える。現地に近くなるほど建物が少なくなる。なにかいいトイレ建物(失礼)はないかな。
「玉川ダム」「見学可能」
ダムの見学は楽しそうだな。巨大建築物。放水。ダムカレー。ダムカード。ただし私は高所恐怖症なのだ。ダムは趣味にならなそうだ。埒もないことを考えていると、クルマを止めるタイミングを失った。
八幡平の麓にトイレがあった。ただし「クマ出没注意」とある。「三毛別羆事件」のネット記事も『ゴールデンカムイ』も読んだ。クマを怖がりながら用を済ませて安心する。
ナビはほぼ到着を示している。渋滞。ここで四十分も足止めを食う。なにが起きているのだ。
のろのろ進んだ先にあるのは駐車場だった。係員がトランシーバーで連絡を取り合っている。満車なので一台が出るまで次の一台を入れないのだ。料金を取っている以上、中に入ってから「場所がない」というめには遭わせられない。
看板の地図を見る。初めてわかった。これは登山である。私のような軽装姿もいるが、アウトドアジャケットに登山靴、登山リュックの本格派クライマーもいる。そういえば寒い。ぺらぺら布一枚だがジャンパーを持ってきてよかった。サンダルで来なくてよかった。
とりあえずドラゴンアイを目指すことにする。人の列に着いていけばなんとかなるだろう。足元が雪になった。滑りそうになる。義母を連れてこなくてよかった。五月の一面の銀世界が新鮮でシャッターを押す。いやシャッターは切るものか。三和シャッターのロゴは「シヤツター」と小文字を嫌う。「キヤノン」とか「キユーピー」のようなものか。
「パパぁ」と小さい女の子が駆け寄ってきた。驚いたが私ではない。別の父親に抱きつく。当たり前である。
「もうドラゴンアイを見てきたの?」
お嬢さんはママと一足先に行ってきたようだ。
「うん、あのね、ドラゴンアイはできてなかったよ」 幼稚園児にネタバレされた。
ドラゴンアイを見られるかどうか、胸を躍らせながらここまで雪道を登ってきたのに。
そういえば娘ポーシャが「パパぁ」なんて抱きついてきたことはあったかな。たぶんあったのだろうけれど、気がついたら電子教材をいじったりピアノを弾いたりする姿ばかり記憶にある。一人旅の孤独。
ドラゴンアイへ。円い池の中に、大きな雪の浮島が浮かんでいる。その周りの水が青く光り、たしかに目玉のように見える。これがドラゴンアイか。青い瞳、白い雪、緑の森林が美しい。
八幡平頂上展望台に登って四方を見渡す。
原生林を抜けると雪の平原になる。この変化が楽しい。ガイドブックによると原生林はアオモリトドマツという木からなっているそうだ。おそ松さんのトッティである。
少し肌寒い風が心地よい。空は青く、沼の浜辺は陽の光をきらきらと反射する。
遠くには岩手山も見える。その美しい姿はガヴァドンのようだ。
一時間ほどでレストハウスに戻ってくる。説明ポスターがある。
「ドラゴンアイの中心の雪氷が解けてドーナツ状になることを『顕現』と呼びます。毎年『顕現』するわけではありません。」
外側が青いだけではない。外側の水の青、雪の白、さらに真ん中に青い水が見える姿が真のドラゴンアイだったのだ。私が見たのは半熟ドラゴンアイ。また見に来る理由ができた(負け惜しみ)。
見るべきものは見たので帰ろう(半熟だけれど)。レストランは満員。お土産屋を見て回る。南部鉄瓶、その熊鈴。ああ南部領なのだなあ。一番人気だとポップにあるくるみゆべし、冷麺、ジャジャ麺、東北土産LOOKチョコレートずんだを選ぶ。LOOKずんだは神奈川県の平塚工場で作られている。
台に置かれているかごに手を伸ばす。
「あっ」 眼鏡をかけた若い女性と目が合う。
「あ、どうも、ありがとうございます」
どう考えても先に手を出したのは私なのに、どうして渡してもらえると思った。まあ急いでいるわけでもないので女性にかごを渡す。
「私の分も、すみません」
連れの髪の長い女性も手を伸ばす。二つ目のかごを彼女に渡す。
「ありがとうございました」と女性デュオは今日の風のように爽やかに去っていった。
あっけにとられたが紳士的に振る舞えたことに私は満足した。
帰宅してスージーにお土産を渡す。
「くるみゆべしは、もう食べ飽きた」