107・電工2種体験記(上)
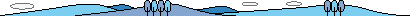
品のないネタは書かないようにしようと思っているのですがちょっと無視できないことがあったので書きます。
先日家族でごはんを食べに行きました。私と妻のスージー、娘のポーシャ、そして義母です。一時間ほどのドライブです。帰り道スージーが「しりとりしよう、り!」と元気に始めました。私は「ず」で「ずうとるび」しか思いつかなくて降参しました。その後ポーシャは「図画工作」「随筆」と切り抜けていました。それはいいです。
義母の番「ち」。
「ちんちん」
それは駄目だろう。しりとりだぞ。品がない上にゲームの約束を守る気がない。しかも高校生の孫の前で何を口にしているのか。二重三重に道を踏み外している。
さて今年は時間ができたので第2種電気工事士に挑戦する。これがあると家の中の電気工事ができるらしい。私はスポーツタイマーの断線した電源コードをはんだ付けで直したことがあるのだが、これは資格無しでやってよかったのだろうか。
まずは申し込み。ネットでできる。必要事項を入力して顔写真のjpg写真を送信。翌日。「エラー」。顔のせいか。
顔写真の頭のてっぺんが切れているので別な写真を送るように言われる。
筆記試験。問題集をひたすら解く。基礎理論や配電設計から始める。
オームの法則は学校で習った。合成抵抗の計算は和分の積の逆数だ。だが、実際に出題されるのはこんなパズルだ。
「並列の4Ωと4Ωを合わせて2Ωになり、直列に並んでいる2Ωと合わせて4Ωになり、さらに並列になっている4Ωと合わせて2Ωになります」
内容は難しい。三相交流なんて何度やっても当たらない。わかったのはインピーダンスだ。ステレオまわりで聞かれることばだが、抵抗のようなものだ。コイルやコンデンサの抵抗に当たるものをリアクタンスという。抵抗とリアクタンスを合わせたものがインピーダンスだ。それ以外のことはよくわからない。インピーダンスって何だっけ。
前書きにも弱気なことが書いてある。
「試験は百点満点で60点が取れれば合格なので、前の方にある『基礎理論』や『配電設計』は無理に解かなくてもいいですよ(意訳)」 問題集としてそれでいいのか。
本の中盤から終盤にかけては工事の決まりや部品の名前を覚えること(鑑別という)が中心でなんとかなる。詰まったのは配線図。一本の線で器具をつないだ図が示される。もちろん電気は行きと帰りと二本つながないと流れないので、二本の線でつないだ図に書き換えるのだ。いくつか書いているうちに「(スイッチ以外の)すべての器具を並列つなぎにする」ことがわかればいつの間にかできるようになった。ありがとう学研の「n年の科学」。
技能試験キットを買っておこう。合格が決まってからだと品不足になるかもしれないし、実物があれば理解の助けになる、と情報があったからだ。ホーザンという会社の工具セットと対策キット1回分を注文する。
「違法だったか」とびくびくしていたスポーツタイマーの修理もコンセントのこちら側なので問題はないことが判明した。
筆記試験。駅から某大学まで無料のバスが出る。年齢は爺さんから高校生まで。シャープペンシルや鉛筆の芯がなくなったらどうしようとどきどきした。コロナ禍で会話は控えるよう指示があるが、ガテン系の中年たちが「リンスリ問題がわからなくてよう!」と談笑している。電線の太さと本数によってリングスリーブと呼ばれる電線をまとめる器具の種類と刻印が決められている。
試験開始。順調に解いていくが二つわからないものがあった。
一つはコンセントなどの裏側に配線をした写真を見せて、「どの配線が正しいでしょうか? クイズ」。それは技能試験ですることだ。
もう一つは写真を四つ乗せて、「この配線図で使われていない器具はなんでしょう? クイズ」。三つは見たことがあるが一つは見たことがない。その見たことのない器具が使われていない器具、つまり正解。三つわかれば消去法、という意図はわかるが、そういう受験者を戸惑わせるような出題はいかがなものか(ライティングダクトのフィードインボックス=フィードインキャップとも=だそうだ)。
新しい技術が開発されるから今まで出題されないものが出題されるという意味もわかるけれど。
試験は二時間だが、一時間を過ぎたら退出してもよい。どどどど。実際は「退出票」を受け取ってから出ていくので足音はしないが、半分以下になった。皆さんそんなによくできるのか。それともマークシートだから山勘霊感第六感なのか。
一時間半も解答していた私のような人は一割程度しかいなかった。