24・図書の館
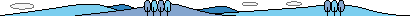
こんな夢を見た。
いつも気になる彼女。今日はいるかなと思ってもなかなか会えない彼女。寡黙で、控えめで。その人が私の目を見つめて微笑む。そしてこう言うのだ。
「ご利用ありがとうございました」 客と店員の関係かい。
生活が苦しくなり、倹約生活を強いられた。油断するとクレジットカードさえ支払不能だ。結婚するとこんなに不自由なものか。休日になると本屋を巡っていたあの日はもう過去。立ち読みは性に合わない。我慢していたが活字に飢えて耐えかねて図書館へ行った。おらおらー本をよこせー。正しくは貸せー。貸してください。たぶん貸してと思う。貸してもいいんじゃないかな。
もう一つ理由がある。「図書館でビデオやCDを借りられる」という話を聞いた。そういえば県庁所在地の図書館にはいっぱしの視聴覚コーナーがあった。世界の名作映画、巷で話題の新作、落語などだ(世界の落語、巷で話題の落語はなかった。)。
大学の図書館にもあったと記憶している。昔の話をなぜ覚えているかというと、当時友達がいなくて、時間を持て余すと図書館で独り時間をつぶしていたからだ。寂しい回想終わり。
さて地元の図書館へ。視聴覚コーナーはどこだ。待っていろ世界の名作映画。世界の名作落語でもいいぞ。
……そんなものはありません。子供向けの世界の名作アニメが一本、あとは『○○川の源流をさぐる』『著作権を考えよう』『市制50年のあゆみ』『よくわかる裁判員制度』なんて広報ビデオのみ。ここは誰も見ないビデオの姥捨山か。もちろんCDなんてない。キャッシュディスペンサーもない(普通ありません)。
と、ここまで書いてきて全国の図書館勤務の方々の怨嗟の声が聞こえてきそうだ。これからハッピーになりますよ。ならなかったら、それは気のせいドリアード。
それでも何度か借りているうちに、じわじわ快感が生まれてきた。
コンピュータによる蔵書検索端末がある。「レーザーディスクは何者だ」と歌われるレベルの田舎なのに。
何冊借りてもロハだ。十冊まで借りられるらしい。
子供のころ、父親に連れられて図書館に行き、時間をかけてたった一冊を選び、待ちきれなくて帰りの車内で読み、車酔いになってしまったことが思い出される。酔うとわかっていても読んでしまうのだ。その父も、その図書館も、今はない。切ない回想終わり。
寿司屋や飲み屋で「そのメニューにあるの、端っこから全部」なんて言えないが、図書館では「ある作家の本を、左から順に借りる」なんてのも朝飯前だ(自慢になりません)。
私は無駄遣いが嫌いだ(ただのけちである)。冷蔵庫の食材を忘れて捨てるときなんて、いちいち断腸の思いだ。そんな私が、まだ途中なのに期限が来てしまった本を、さらりと返却できるのだ。だってまた借りればいいし。レンタルビデオだと「お客様、これは一度借りられていますが」とおせっかいを焼かれるが、ここではそんなことはない。1ページも読まないまま返したっていいのだ。
本屋と違い、選んだ本を手提げに入れられるのもいい。
などと書いていると書店の方に怒られそうだが、実際は逆で私の近所では、三軒が店仕舞い、一軒が移転してしまったのだ。どうなってしまうのだこの町。文化的に退行している。再来年には石器時代かな。
店員さん、ではない、係員さんがここで登場する。係員さんは複数いるが、気になるのは地黒で若い女性だ。この人がまったくしゃべらない。唖なのかな、と思う。近くの市役所には車椅子の人がいた。アファーマティブアクションというやつであろうか。黒っぽい女性に話を戻すと、私が「お願いします」「ありがとうございました」と意識的に声を出してもサイレントなのだ。そんなのがいっぱいいたら、サイレントマジョリティーか。「声を出したら打ち首」「磔斬首獄門」という就業規則があるのかと思ったが、ほかの係員さんは発声する。黒女だけだ。暗い感じがする。係、陰惨。
今度、「夏目漱石の本はありますか」などと質問してやろうかと思うが、本物だったらと思うと聞けない。意外と黙ってデジタル検索端末を指差すような気もするのだ。