21・ヘルスなセンター
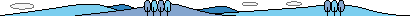
――流血の宴。
――脱衣の強要。
――飢餓の苦しみ。
――回転台での拷問。
――弄(まさぐ)られる体。
レッツ、人間ドック! 犬じゃないぞ、人間ドック!
八月某日。私はとある保健センターに向かって、愛車ステップワゴンを走らせている。
人間ドックは初めてではない。ただ過去2回とも病院においてである。ドックに特化したセンターの営みを体験するのも、有意義なことであろう。特に私は酒を飲む。毎晩飲む。十代のころにそんな習慣はなかったが、いつの間にかそうなった。酒税法における、タックスペイヤーである。どこかに「この施設は酒税によって作られました」という旅館があったら、私はリムジンで送迎してもらえるはずである。銅像だって建立されてよい。
受付時間は8時30分だ。混雑するのが常なのか、パンフレットには「早く来た方は番号札を受け取ってください」とある。あまり早く終わると、会社に戻らなければならない。ゆっくり行こう(出社義務がなければ一番の札を取る自信はある)。大人の余裕だ。
――到着、8時33分。看護婦さんの説明が始まっていた。思いっ切り遅刻。
さて、病院と来れば看護婦さんである(ここは病院ではないが)。ちなみに当サイトでは看護師という呼称は使わない。個人的な理由を開陳する機会を友好的に行使する手段を幸甚にもいただけるのであれば、韜晦するより論述したく思いますので申し上げますが、男はいらん。
遠慮がちに360度見渡すが、みなさん私より年上のようだ。ううむ。でも私好みの170センチ(推定)が一人いた。
さて採血。4人の看護婦さんがいる。フォーク並びで空いたところに入るのだ。せっかくだからきれいなお姉さんに血を吸ってもらいたい。あ、4人の中で最も質量のありそうな、ホンジャスカの太っている方に似ている人が終わりそうだ。アーメン。
……ホンジャスカさんは何かが切れたのか、カーテンの陰に消えた。いえーい。
それなりの方に吸血、いや採血してもらう。
「真っ直ぐで取りやすい、いい血管ですね」とほめられる。
本当に? そういえばずっと人にほめられたことなんてないなあ。中年に片足を踏み入れた年代で、これは心に染みた。……ほめられちゃったよ。なんか、泣けてくる。
視力検査。私は眼鏡もコンタクトも持っているので、経験値は豊富だ。台詞は「わかりません」ばっかりだが。
あれ。見たことのない機械だ。二つのレンズをのぞき込むのは普通だが、手元にジョイスティックとボタンがある(女医スティックではない)。ちょっとMSXライク。ランドルト環の切れている方向にスティックを倒すのだ。見えないときはボタンを押す。ところで、PSだのウィーだの、現在のコンシューマ機はすべて女医パッド、ではない、ジョイパッドになってしまいましたね。思わず16連射してしまうところでした(嘘)。
眼底撮影。このセンターでは「初めてですか」という質問をよくする。はいと答えると意義や方法を丁寧に説明してくれるのだ。ちなみにここでは、「眼下は人間の体の中で唯一血管を見ることができる部分で、動脈硬化がないかなど、血管の様子を見ることができるのです」という意味の説明をいただいた。ありがとう看護婦さん。眼底だけに、これからもがんばってえ。
ソファに座る。ゆったりとしたものだが、隣りに座る女性とはずみで肩が触れ合う。服装はガウン一枚である。女性はティーシャツくらい着ているかもしれないが、私はガウンの下はパンツ一枚である。慣れぬ女性の香りにくらくらする。
しかも私は「こんなときでないと、読まないであろう」と図書館から借りた『ジョイスへの道』なんて専門書を手にしている(よせばいいのに)。そのジョイスが奥さんに出した手紙がまずかった。
……むかしリングズエンドで君に触れたのは僕の方からではなかった。君の方からだった。君の手を僕のズボンに滑り込ませて僕のシャツをそっと引っぱり出して僕の○○○を君の長いくすぐる指で触れて大きく固くして、君の手に入れてゆっくりと愛撫して僕は君の指の間で果ててしまった。(略)男の下になっているのに倦きて、ある夜、君はシュミーズを荒々しく脱ぎすてて裸で僕に馬乗りになった。僕の○○○を君の×××に突き刺して激しく僕を乗り回したっけ。おそらく僕の角笛が君には十分大きくなかったのだろう、というのは思い出すんだけど君は僕の顔にかがみ込んで優しくささやいた――「あなた、もっと△△△△を! あなた、もっと△△△△を!」って。
ジョイスはHENTAI趣味か。あるいは、こういう手紙を、作家だからって書簡集として後世に延々と遺すって、文学研究者ってまずいのではないのか。作家になるのならおちおち手紙も出していられない。
当惑したのは肺機能である。なにやらプラスティックの管の先端をくわえさせられる。「吸って――吐いて――ずーっと吸って――はい思い切り吐いて!」と言われるままに呼気吸気するのだが、どうしても弱いようである。昔の機械のように、「思い切り吸って、はい吐いて!」ならシンプルだが、いちいち指示を聞いてからなので体が十全に動いてくれない。相手が蛇腹でなく、コンピュータ仕掛けのセンサーだからかもしれない。「もう一度」
ぷうーっ、よしやった!と思ったら、「息が舌にぶつかりましたね」と言われる。確かにそうだ。なんでそんなことまでわかるのだ。
……結果、肺年齢は実際より4歳も上に診断されてしまった。
そして最終チェックポイント、胃造影検査。いわゆるバリウムである。私はバリウムを飲むのは苦手ではないので、さらりと進行。
しかし途中でロボットアームがおなかを押すのには参る。ある程度で止めてくれるだろうとは思うが、「このままアームが寝台まで進んだらどうしよう」「内臓破裂は助からないな」などとダークな思案ばかり浮かぶ。たぶん70年代SFの、ロボットの反乱がトラウマになっているのではないか。病院マザーコンピュータの暴走。武器はメスとカルテと滅菌ガーゼ。
終了。男性は午前で終了だ。女性には「マンモグラフィーを受ける方、こちらに」と声がかかる。
マンモグラフィー。すごい名前だ。どうしてもギャートルズを思い出す。マンモー、英語で"mammal"と言えば、哺乳類の動物のことだ。ほらやっぱりギャートルズ。
最近、メタボリック症候群の診断が厳しくなったとかで、看護婦さんの説明を受ける。おお、初っぱな気になっていた長身の女性ではないか。「こちらへ」と曲がり角の陰に案内されてなにやらいい気分になる。ソファに二人掛け。もう駄目だ(リビドー的な意味で)。
そして二人きりの甘い会話を交わす。
「食習慣があまりよくない」
「肺年齢が実際プラス4」
「煙草は吸わないのにねえ」
「メタボリック予備群」
「学生時代の体重はなんキロでした?」
「あらそう、……それに戻すのは難しいかもしれないけれど、できるだけ落としたいわね」
「肝機能障害の疑いがある」
「体は休んでも肝臓が休めない」
「肝臓の傷ついた細胞がぽろぽろとはがれ落ちている」
――そして二人の指は、触れ合った(保健センターの名前入りの封筒に入れられたファイルを受け取っただけ)。
ドクターの診断。
「大きくは悪くない」
「(胃痛があったというが)胃も悪くない」
「煙草は吸わないから、肺がんの可能性は少ないが、本人の運命というものもある」 なんだそれ!
「γ−GTPなど肝臓の機能低下が見られる」
「休肝日を作らないといけない」
「禁酒は大変でしょうが、一日に飲む量を少なくしましょう。長く生きてたくさん飲むために」
わかりました先生。
……。
帰宅。ちゃかちゃかと、この文章をタイプする。ふう。一息つく。
ロックグラス。
ウヰスキー。
氷水。
さて今夜も飲もうか。健康に、乾杯。