14・冬のオフィシャル
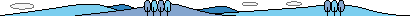
また来てしまった。某スキー大会。六年ぶり二回目、なんてまるで紅白。
今回の役職もコンピュータ係だ。聞くところによると、ほかの係はもっと大変らしい。旗門員は寒い中ずっとコースの端っこで待機し、旗門が倒されたら直す。直しているうちに次のランナーが猛スピードで突っ込んでくるのでそれを命からがら避ける。以下繰り返し、だそうだ。何そのシジュフォス。
前回の仕事を思い出す。クロカンのタイムをエクセルに打ち込む、という仕事だった。ただし形式や内容が朝令暮改で変わり、そのたびごとに表計算シートを訂正する、先の見えない、いや柔軟性を必要とされる仕事であった。
二度めだ、きっとうまくこなせるであろう。
「おはようございまーす」
とりあえず仕事はない。「上司」が来るまで談笑し、ネット張りの手伝いをする。これはネットワークケーブルではなく、ただの網だ。ゴールを囲むネットだ。網を張るとちゃっかり「がんばれ○○!」なんてのぼりをくっつけるのがおかしい。ゲレンデだから「カレー」「生ビール」なんてのぼりの方が似合うだろう。
上司が来た。何やら機械とパソコンを接続している。ソフトが立ち上がる。USBメモリを挿し、データをコピーしている。ええと、あのう、私の立場は。
いや、ここで指示待ちになってはいけない。私だっていい年だ。自分から動くのだ。
「コンピュータ係のパトリックと言います。今日はよろしくお願いします。あとで操作方法を教えてください」
「はい。簡単ですよ」と言った上司は、そのまま機器の操作を続けた。私の存在も簡単に流された。
我々が入っているのは、ゴールハウスと呼ばれる八畳ほどの箱である。その箱に爺さんが入ってきた。ウェアに貼られたワッペンや名札が、その地位が高いことを物語る。でももっと雄弁なのはその態度だ。怒鳴るのがデフォルト。断りなしに煙草を吸う。こういう人には近付かないようにしよう。偉い人には近付かないの法則。
レースが始まった。六年前はトランシーバーから入ってくる数字を聞いて、エクセルに打ち込んでいたのだ。ところがだ。現代技術恐るべし、ゴール判定装置から直接パソコンの専用ソフト「ゲレンデシステム」に数字が入ってくるのだ。ランナーの名前、通し番号、所属付きで。さらに全自動でプリンタから「短冊」と呼ばれる順位カードが吐き出される。つまりだ、私の仕事はないに等しい。
いやこれが大学生のアルバイトなら喜んだであろう。ちょっと待って、パソコンに詳しい人ということで私が呼ばれたのではないのか。ランナーのスタート、ゴールをすべて機械が感知する。私がしたことはせいぜい、DS(ドント・スタート=棄権)、DF(ドント・フィニッシュ=途中でリタイア)を入力することだ。中学生でもできるぞ。
昼休み。配給が来た。「もう一つ欲しい人?」との呼びかけに対して、お握りのお代わりをしてしまう。ストレスを食欲で満たそうというのだ。「たいした仕事もしていないのにお握りお代わりしたんだって」と言われてるのではないかと、疑心暗鬼におちいる一日目。
一日目、終了。上司に尋ねる。「明日は何時に来ればいいですか」
「うーん」 悩むなーっ。
「競技開始の前に来てもらえれば」
これはもう、配慮だ。大会事務局は二つに分かれている。スキー連盟の専門家と、我々のような派遣された者とだ。次回参加する保証はない派遣に手取り足取り教えるよりは、専門家が要所を押さえた方がいいのであろう。まったく正しい判断である。
二日目。昨日は朝早く来ても仕事がなかったので、一時間遅く到着。大勢にまったく問題なし。せいぜいプリンタの紙をさばいて、仕事をしたふりをする。
競技開始。なんと今日はDFすら、現代技術が自動判定してくれる。おそらく規定の時間を過ぎるとそう判定するのであろう。電気時計係や放送係がせわしく業務をこなす中、私は何も仕事をしないのが仕事だ。
いや、わかっているのだ。私のちっぽけな充足感より、大会を運営する方が大事だ。コンピュータで何かトラブルがあったときのために、私はいるのだ。自衛隊と同じで、私の出番はなければいい。
それでも、私は、だんだん、眠く、なる。落ち、かかる、意識。
「紙がありません」 掲示係の女の子の声だ。
見れば、プリンタの紙が尽きようとしている。ようし、私の出番だ。慣れた手つきでPPC用紙をレーザープリンタに装填する。
「ありがとうございます」と掲示係。いや、いいってことよ。礼には及ばないぜ、かわいこちゃん。
ぴーぴーぴー。
「用紙がつまりました」
あああ。
この間にもランナーは滑走し、30秒間隔でゴールしていく。これはまずい。紙を入れ直す。ふたを開ける。詰まっていた紙を取り出す。幸いにもその紙はちょっとしわになっただけで、使えそうだ。まだエラーランプは消えない。慣れないプリンタだが、そんなことは言っていられない。動揺を隠して、開けられるふたはすべて一度開けて閉め直す。プリンタエラーの法則だ。
「ぶーん」 再びプリンタは動き出した。山場は、越えた。
ここまで雑文としてどうだろう。やはりここは失敗しないと、雑文のネタにならない。私の雑文は、10%の言語学と、20%のセンチメントと、80%の恥ずかしさでできている。計算を間違えた。
ランナーが我々の目の前で、転倒した。時計係が思わず「転んだ」とつぶやく。
「今、転んだ、と言ったのは誰だ」と怒鳴り声。例の偉そうな爺さんだ。オフィシャルはそれさえも許されないのか。恐るべしスキー界。
「このパトリックっていうのは、どんな人だ」
例のえらそうな爺さんだ。いきなりぶしつけな。どんな人、と言われても。かと言って周りの誰かが「パトリックとは○○出身で○歳、趣味はコンピュータ、好きな食べ物はスパゲティ、好きなアイドルはフキイシ一恵」なんてしゃべり出しても困る。自分はそんなに簡単に説明されていいのか。ここは自分から行こう。
「はい私です」 傍若無人な爺さんだけに、一体何を言われるのか。
「あんたの出身はどこだ」
素直に答える。
「○○さんの旦那さんか」
「いいえ」
「○○さんの息子さんではないのか」
「いや、聞いたことはないですね」
……会話終了。
後になってわかったことだが、爺さんと私は苗字が一緒で、それで興味を持って尋ねたらしい。競技中だというのに。
競技終了。すぐに撤去が始まる。ここは山の中腹、下まで歩くのは結構ホネだ。私はすることがないので、上司に尋ねる。
「何かできることはありませんか。ゴミ袋でも持って下がりましょうか」 そうなればいいな、と期待を込めて言う。
「あー、ちょっと待っていてください」 待つ。
役員のうち、スキーをはいているのは二割だ。インスペクションをする、あるいはネットを担いで滑る人たちだ。ほかの七割は自分の足で上がり下がりする。スノーモービルと雪上車を使うのは、限られた人たちだけだ。
で、私はと言うと、スノーボードである。私だけだ。
「はい、パトリックさん、持っていってください」とゲレンデシステムの一部の入ったジュラルミンケースを渡される。
ええと、こういうのって、需要が少ないので高価なんですよね。六桁、いや七桁。いくらジュラルミンに完全密封、発泡スチロールで固定とはいえ、無事に下りられるだろうか。
スキーなら大丈夫だ。スキーなら下まで40秒。しかしボードでは。しかもジュラルミンケースは二つだ。けっこう重い。これでバランスが取れるのか。
これを持ったまま大転倒したらいいネタになるなあ、と思いつつ、それはちょっとできない。六年の重みだろうか。ここで失敗したら帰るのが遅くなる、という現実的判断に基づくところもある。
結局、ケースを両手に提げたまま、歩いて下山した。繰り返すがスキーなら40秒、ボードなら3分というところだ。緩斜面になったらボードを付けようかと思ったが、それも断念。緩斜で転倒したらそれこそ末代までの恥ではないか。
ケースはまだしも、ボードを持って坂を下りるなんて笑ってしまう。
下山。ボードを置いて、役員会議へ集合する(実際は雪の中40人ほど輪になっただけ)。
「お疲れさまでした!」
実行委員の音頭で唱和、拍手。ああ終わった。
「お握り余っていますのでどうぞ」
くださいください、と役員室に入っていく。
「いや、外で配りますから」
まるで自分ががっついているようではないか。事実そうだが。いただきまーす。
……待て、六年前と同じではないか。自分の進歩のなさにあきれる。
風雪がひどくなってきた。早く帰ろう。スキーウェア越しに、クルマのリモコンキーを開ける。キーを挿して、エアコンをかけ、暖気しよう。
え? キーの入ったポケットの、ファスナーが開かない。もうパニック。眼鏡は曇るし、手はかじかむし。焦る。最高気温二度の世界である。かじかんだ指に力を入れるとどれほど痛いか、経験者は御存知だろう。
永遠と思える一分ほど焦慮したのち、開けることに成功。これで帰れる。エンジンスタート。ウェアとサロペットを脱ぎ、スニーカーに換え、窓の雪を払う。ステップワゴン、発進。
何か、何か足りない気がする。
振り向く。荷室に、愛用のスノーボードがない。
役員会議のため置いてきたままではないか。