176・人間ドック闘病記(前編)
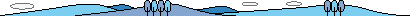
人間ドックが好きだ。
切れ目を入れたコッペパンに人間と茹でた大振りなソーセージとベビーリーフを挟み、ケチャップとマスタードを波模様にかけ、軽く火で炙ったのをがぶりと食うのがたまらない。ニンゲンのホットドッグ。巨人の屋台か。
やり直し。私の会社では若い頃は三年に一度、今では二年に一度(!)、人間ドックに行く資格が与えられる。病院に電話をして予約を取るのが第一関門。その予約の日に出張が入らないのが第二関門。毎年のこの時期はどきどきする。
人間ドックには前夜祭がある。胃検診があるので前の晩は八時までに飲食を終えねばならぬ。だからその日は仕事を前倒しして定時に帰れるよう段取りを付ける。ところがこの日は外部からの連絡を待たねばならず、三十分ほど遅くなる。
帰宅して鬼神の速さで晩酌の支度をする。時計は午後六時。あと二時間しかない。ローマ貴族のような貪欲さで二時間の晩酌を急ピッチでエンジョイする。
当日。ナースさんたちに失礼があってはならんとシャワーを浴びる。ドック受診者は具合がわるいわけではないので道路の向かいの駐車場に停めるのがたしなみだ。
エレベーターへ。入って奥へ進むと「すみません」と一人、また一人と乗り込んでくる。合計四人。行き先は同じ。ぽんぴん。入口に近い者から降り、私は最後に降りた。ちょっと待って。先に来たのは私だかんな。ファースト・イン・ファースト・アウトであろう。四人パーティーはすたすた進み、人間ドックの受付札のところで先頭の人が「(どなたが一番ですか?)」と目で合図した。イッツミー。譲られて遠慮なく札を取る。わが町は民度が高い。
何度も来ている病院なので、流れはわかる。番号を呼ばれ、受付で書類や検便を渡す。数年前別の場所で受けたときはいつまでも検便を持たされて不安になったものだ。保険証のコピーを取られる。便利だよね、紙の保険証(政治的風刺)。お薬手帳も預ける。書類に「お薬手帳預かり」というハンコを押してもらう。「このハンコがあればきっと返してくれるのだろうな」とうれしくなる。
受付を終え、更衣室に入る。ロッカーがある。服がない。どこだ。ドアを開ける。別のお客さんが衣装を来ている。
「ああう…」
「服ですか、こちらですよ」 親切に教えてくれた。
服は更衣室の外に並べてあった。
上半身はシャツのようにかぶるが、お腹の前で裾が互い違いに二枚になっているという「ドック服」としか言いようのない不思議な服である。下半身はチャックもなにもない「ドックもんぺ」である。
検査は三つの段階に分かれる(私の勝手な分類)。まず上階の専用スペースで血液検査と血圧測定で肩慣らし。次に一階の普通の診療棟に行き、心電図、腹部エコー、尿検査、胃レントゲン(または胃カメラ)という本日のクライマックス。最後に上階に戻り、身長体重、視力聴力、メタボ測定、眼圧、医師診察、保健指導で終わる。……終わるはずだった。
血圧が低い。上が106という信じられないロースコアを出した。いつもは140くらいなのに。人間ドックを信じ切ってリラックスしている。
尿検査が終わり、レントゲン室前で待つ。本日のメインイベントである。バリウムを飲むのは苦手ではない。レントゲン台(なんというのか)の上でぐるぐる回転したり台を傾けられても落ちないようバーにしがみついたりする難事はすでにスポーツである。
名前が呼ばれた。どんなにぐるぐるされてもしがみついてやるぞ。
「発泡剤をお飲みください。げっぷを我慢して」
粉末を飲む。小学校のころ科学クラブで重曹とクエン酸でぬるくてうまくもなんともないサイダーを作ったことを思い出す。
「次にこれをお飲みください」 パトローネ大のコップに透明な液体が入っている(パトローネの喩えは通じるのか)。飲む。
胸が苦しくなった。
手で胸をさする。
体が前後左右に揺れる。
げっぷがもれる。
うめいた、と思う。あまり記憶がない。
ナースさんに「座って、座って!」と指示されるがひざが動かない。
救援に別のナースさんが呼ばれる。
……ようやくその場に座り、落ち着く。話ができるようになる。
「別のところでお休みしましょう」とナースさん。
車椅子に乗せられて、レントゲン室を出ていく。ベンチに座っている客が悲痛な目を向ける(向けたような気がした)。
「あっ、パトリックだ」 会社の健康診断だから知り合いもいる。
「なにかあったに違いない」
「歩けないのか」
「レントゲンで重篤な疾患が発見されたらしいよ」
そんな目で見ている。